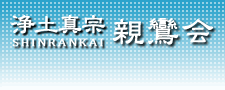私一人がための弥陀の本願
「念仏申し候えども、踊躍歓喜の心おろそかに候こと、また急ぎ浄土へ参りたき心の候わぬは、いかにと候べきことにて候やらん」と申しいれて候いしかば、「親鸞もこの不審ありつるに、唯円房、同じ心にてありけり」
『歎異抄』
共感を呼ぶ第9章の対話は、唯円の率直な問いに始まります。
「私は念仏を称えましても、天に踊り地に躍るような喜びが起きません。また、浄土へ早く往きたい心もありません。これはどういうわけでありましょう」
意外にも聖人は同調されています。
「親鸞も同じ不審を懐いていたが、唯円房、そなたもか」
平生に弥陀の救いに値えば、後生は必ず浄土に往けるとハッキリします。その大安心は、どんな幸せとも比較になりませんから、真宗宗歌には「永久のやみよりすくわれし 身の幸何にくらぶべき」と讃じられています。かかる無上の幸福に生かされたら、躍り上がるほど喜んで当然なのに、「踊躍歓喜の心なし」と懺悔されているのです。
続けて聖人は、
「よくよく案じみれば、天におどり地におどるほどに喜ぶべきことを喜ばぬにて、いよいよ往生は一定と思いたまうべきなり」
と述懐されています。喜ばぬ心が見えるほど、いよいよ喜ばずにおれないと仰った、歓喜無量の発露です。
この不可思議な信仰を理解するには、まず真実の自己を知らねばなりません。仏教ではすべての人間の本当の相を、「煩悩具足の凡夫」と説かれています。「煩悩」とは、私たちを苦しめ罪を造らせるものをいい、そんな心しかないことを「具足」といいます。人間は108の煩悩の塊なのです。
煩悩といえば欲や怒り、愚痴がよく知られています。しかし聖人は
「喜ぶべき心を抑えて喜ばせざるは、煩悩の所為なり」
と仰せられ、喜ぶべきことを喜ばせないのも煩悩だと諭されています。広大無辺な世界に救われながら少しも喜ばぬ、痺れ切った恩知らずこそ、煩悩にまみれた人間の実相なのです。
そんな極重の悪人である煩悩具足の凡夫を、阿弥陀仏は「そのまま救う」と誓われています。だから弥陀の誓願に疑い晴れた人は、喜ばぬ自性を照らされるほど、「こんな煩悩具足の私一人を助けるための本願だった」と感泣し、往生間違いなしと大慶喜するのです。
そして聖人は、一息切れたら弥陀の浄土と明らかだけれども、死に急ぐ心はないし、体調がすぐれぬと、死ぬのでないかと心細くなると告白されています。かたじけなくも娑婆への執着をさらけ出し、煩悩の激しさを浮き彫りにしてくださったのです。
煩悩具足の者をお目当ての本願まことだったと、一日も早く聞き開き、広遠な仏恩に報じ奉りましょう。
(R5.12.15)