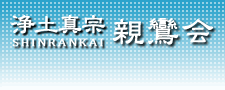弥陀の洪恩と田植え歌
三度の「ご飯」は、「米」を買って研いで炊くだけ、という人がほとんどでしょう。ですがその米ができるまでは、俗に「八十八」といわれるほどの手間がかかります。特に機械のなかった時代の重労働は、現代人には想像もできません。
阿弥陀仏のご苦労を、親鸞聖人が稲作に関連づけて教えてくださったことがあります。それは泥田につかり、農家の人々と田植えをされながらのご布教でした。生きることに精一杯の庶民に、仏縁あれかしと田植え歌を作られたのです。
「五劫思惟の苗代に
兆載永劫の代をして
雑行自力の草をとり
一念帰命の種おろし
念々相続の水流し
往生の秋になりぬれば
この実とるこそ、うれしけれ」
農家では春に田を耕し、苗を育てる苗代を作ります。しかし稲作に適した平地が、どこにでも転がっているものではありません。先人が血と汗で荒れ地を開墾したのです。大木を切り倒し、入り組んだ根っこを取り除き、大きな石を粉砕して除去するなど、どれだけの骨折りがあったことでしょう。
田んぼを鍬や鋤で掘り起こしたあと、水を入れ土を砕いて平らにならす「代かき」が必要になります。それら粒々辛苦に例えられたのは、弥陀が幾億兆年どころでない、五劫の永きにわたって思案され、さらに兆載永劫という、想像を絶する長期間のご修行の末に、大宇宙の功徳の結晶「南無阿弥陀仏」を完成なされたことです。
この六字の名号を与えて救うと、弥陀は命を懸けて誓われています。しかしその誓願を疑う「雑行自力」の心が邪魔をし、名号をはねつけているのです。
農家の人に「雑草」といえば、取らねばならないものと分かるから、「雑行自力」を身近な草になぞらえ、一切の計らいを捨てよと教示されています。ですが無始より迷わせてきた自力は、一朝一夕に除けるものではありません。小さな石と思って掘っていくと、畑一面の大石だったと驚くようなもので、聞けば聞くほど、強情な自力の大盤石に泣かされるのです。
弥陀の本願を聞き開き、「まことだった」と疑い晴れた時が「一念帰命」。その一念に、名号・南無阿弥陀仏の仏種がわれらの心中に徹底し、無上の幸福に救い摂られるのです。
その喜びから、寝ても覚めてもお礼の念仏を称えずにおれなくなる「念々相続」を、田に流し続ける水に例えられています。
秋の収穫で表されたのは、平生に救われた人が、命終わると同時に浄土に生まれ、仏果(仏のさとり)を得て永遠の幸福に生かされることです。
帰命の一念まで聞き抜き、如来聖人の洪恩に報い奉りましょう。
(R6.3.15)